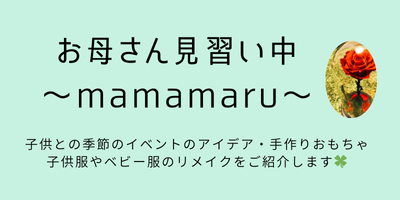スプーン・フォーク・はしの3種類を置ける子供用の箸置き(カラトリーレスト)を手作りしましたのでご紹介します☆
2歳・4歳のわが子たちは,お箸がまだ上手に使いきれないので,食事の時にスプーン・フォーク・お箸の3種類を使います。
そのため,食事のときに使ったスプーンやフォーク,箸が机のいろんなところに置かれ,食べているうちに手に引っかかって落ちてしまうことがよくあります。
拾って洗っては落ち拾って洗ってはまた落ち…の繰り返し…
箸置きがあったら使わない時の置き場がはっきりしてよいのか!と思いつきネットで探してみましたが,なかなかスプーン・箸・フォークの3種類を置ける可愛い箸置きがありませんでした。
そこで自分で作ってみることにしました★
簡単に可愛くオリジナルの子供用箸置きが作れたので,実際に作った【えだまめ箸置き】・使ったキットなどご紹介します。



(2025年1月に新幹線バージョンも追加作成しました。)
おすすめの箸置き作成キット
今回使用したのがこちらの↑↑【オーブンとうげいキット】です 。
おうちのオーブンで簡単に陶器の箸置きを作ることができます。
今回このキット1つで子供用の箸置きを4つ作ることができました★
100均にもオーブン粘土が売っているのですが,コート剤は別売り。
そして,何件か100均を周ったのですがオーブン粘土は置いてあっても食器や箸置きとして使うために必要な専用のコート剤がおいていない店舗ばかりでした。取り寄せしてもらうのも手間ですし,粘土もコート剤もそれなりに量があり,はしおきを作った後残りをどうしよう…という思いもあったので,100均でそろえるのは断念しました。
こちらのキットは500円程度ですが,粘土に加えて専用のコート剤がついているのでこのキット1つで完結することができます★作り方の説明書も付いていてとても分かりやすいです(^^♪
実際に作った【箸置き】がこちら!!



3つのくぼみにそれぞれ箸・スプーン・フォークを置きます。

【箸置き】の作り方(えだまめ箸置きで説明)
1,粘土を形成する
粘土の1/4を細長く伸ばし,プラスチックスプーンでくぼみを作ります。
最後に箸を豆の房の形になるようにとがらせて形成しました。
箸置きの横の長さは10cmです。

2,乾燥させる
今回は揚げ物用のバットの網にクッキングシートをひいて,その上において乾かしました。表のまま1日,裏返して1日乾かしました。

3,焼く
説明書では「160-180°で約30分焼く」となっています。自宅のオーブンの温度の初期設定温度が170°だったので,170℃で30分焼きました★

4,色を塗る
焼いた粘土にアクリル絵の具で着色します。今回は枝豆にしたかったので緑色で。子供用なので顔も書いてみました★側面も縫って,裏は着色しませんでした。
1日乾かしました。

※着色のポイント
①着色はアクリル絵の具がおすすめ
新幹線の箸置きを作った時にアクリル絵の具の青が足りず,水彩絵の具を使用しました。すると,最後のコート剤を塗るときに塗った絵の具がコート剤の水分で溶けてしました…。なので,着色は乾燥すると水に溶けないアクリル絵の具がおすすめです。
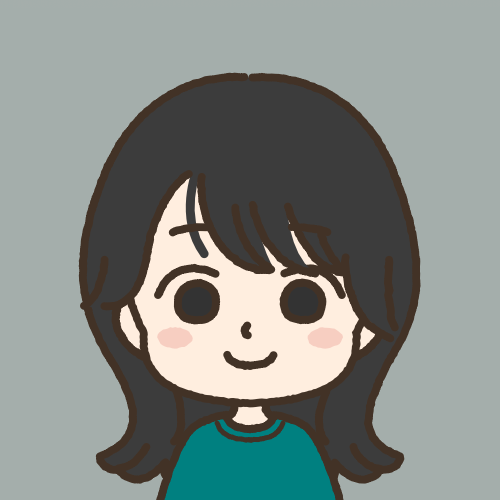
どうしても水彩絵の具を使用するときは,1回目のコート剤塗布の際に,絵の具が溶けることを前提に薄く,さっと塗ることをお勧めします(多めのコート剤を筆を何度も行ったり来たりさせて塗ると絵の具が溶けて柄が汚なってしまいます)。2回目,3回目のコート剤塗布は1回目のコート剤がきちんと乾いていれば問題なく塗ることができます。

↑柄が少しにじんでしまいました
②アクリル絵の具によっては焼きによって色が薄くなることがある
今回は100均のアクリル絵の具を使用しましたが,最後のコート剤塗布後の焼きの後に確認すると,赤と黄色が薄くなってしまいました。絵の具によって異なると思いますが,色が薄くなる可能性もかんがえて濃い目にしっかり着色しておくとよいと思いいます。

↑黄色がほとんど消えてしまいました…

↑赤がオレンジに近い色になりました
5,コート剤を塗る
コート剤は1度塗っては乾かして,乾いたらまた塗ってを繰り返します。コート剤は水のようにさらさらしているので,比較的すぐに乾きます(数分程度)。薄めに塗って乾かすことを表面と側面は4回,裏面は2回繰り返しました。
6,焼く
コート剤が乾いて触れるようになったら,100℃のオーブンで15~30分焼きます。今回は表面で20分,裏がえして10分焼きました。
7,完成!!
コート剤のおかげで表面はつるつるてかてか(^^♪

横から見るとこんな感じです。

実際に使ってみて…
食事の時に「お箸とスプーン・フォークの枕だよ。使わない時はここに寝かせてあげてね」と伝えてみました。
最初のうちはなんとか意識しておいてくれていました(^^♪


ただ,習慣がついていないのでどうしてもまた机のいろんなところに置いてしまいがちでしたが,
「スプーンさんが枕に寝たいみたいよ」
とちょっと声をかけると はっ!として箸置きに戻してあげていました(^^)
習慣づくまで声掛けが必要かなとは思いましたが,やはり決まった位置に箸やスプーンフォークがおいてあると,床に落としにくくなると感じました。
+α 後日 子供と色塗り・絵付けに挑戦してみた★
今回作成した残りの粘土で,同じ箸置きの形で予備で作ってあった箸置きに子供と色塗りをしてみました。
いろんな色を筆で塗るとぐちゃぐちゃになってしまいそうなので,1色決めて全体を筆で塗り,綿棒でお絵描きすることにしました。
ピンクが4歳,青が2歳のわが子です★
4歳の上の子は綿棒なら上手にお顔を書くことができました(^^♪
2歳の下の子は綿棒でくるくる色塗りをしている感じでしたが,いい感じの柄になりました(^^♪


コート剤を塗り焼くのは私が行いました★
よくある陶芸の絵付け体験?がおうちでもでき,「今日の箸置き使う!!」と大喜び(^^)子どもたちにとっても楽しい経験だったかなと思います。
まとめ
今回は【手作り子供用箸置き】をご紹介しました。
3つのカラトリーがおける箸置きがあると,こどもも大人もスプーンやフォークが落ちることで何度も拾って洗って…を繰り返すストレスが減ると感じました。
また,今後も食事の時には箸置きを利用していく機会が子ども自身も増えていくと思うので,食事のマナーを身に着けるという意味でも箸置きを利用するのは良いのかなともいました。
自分で作るというと材料費や作る手間を考えてしまいがちですが,500円程度のキット1つで無駄なく簡単に作ることができるのでぜひお試しくださいね☆



最後まで読んでいただきありがとうございました★
mamamaru🍀
トイトレグッズも手作りしています↓↓よろしければ読んでみてくださいね☆